1985年に創業し2025年は開業40周年イヤー。「食のエドモント」と称され、都心にありながら閑静なエリアに位置するホテルメトロポリタン エドモント。他のホテルに先駆け2018年から食品ロス削減を中心に環境対策に取り組み、「食」の分野では3010運動やもったいないメニュー、食べ残しの持ち帰り「mottECO」、未提供のパンをアップサイクルした「ラスク」の販売、「宴」の分野では宴会プラン「CO₂ゼロMICE®」、「泊」の分野では「CO₂ゼロSTAY®」を導入しています。また、2025年3月にはSDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice(通称:サクラクオリティグリーン)」の「4 御衣 黄(ぎょいこう)ザクラ」を取得。
ホテルが環境配慮に取り組む意義や経緯、CO₂ゼロSTAY®導入についてお話を伺いました。
※CO₂ゼロMICE®、CO₂ゼロSTAY®は、
JTBコミュニケーションデザインが提供するサービスです

ホテルメトロポリタン エドモント

2025年6月にエドモント総支配人を退任し、現在は日本ホテル全体の食品ロス削減の取り組み支援、日本ホテル協会のSDGs委員を務め、政府の食品ロスに対応する食べ残し持ち帰りガイドライン検討会の構成員も務め普及活動に力を入れている松田顧問に食品ロス削減の取り組みを伺いました。
「当ホテルは宴会場やレストランを所有するフルスペックホテルのため、大量の生ごみが発生することが1つの課題でした。日本ホテル株式会社中村勝宏統括名誉総料理長が2017年にFAO(国連食糧農業機関)の日本担当親善大使に任命されたこともきっかけとなり、2018年から全社的に食品ロス削減に取り組み『3010運動』などを展開し、また食材の購入からお客さまに提供するまでの過程でどこに食品ロスが発生するか洗い出し一つ一つ解決していきました」と、松田顧問は振り返ります。
例えば、規格外野菜の購入や、近くの産地から食品を調達するなどカーボンフットプリントに着目。またアップサイクルしたラクスの販売など、知恵と工夫により具体的な取り組みに繋げています。
取り組みの検討を開始した翌年2019年(6~10月)は、前年同期間の対比で、総生ごみ量が約16%削減しました。

日本では、食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」が年間464万トンあり、そのうち231万トンが事業系食品ロスです。その中でも66万トンが外食産業であり食べ残しによるものが相当程度を占めています。(2023年度推計 消費者庁、農水省資料より) 当社では『3010 運動』など食べきりの取り組みを進めてきましたが2022年より『mottECO(モッテコ)』の取り組みも始めました。これは、ホテルのレストランや宴会場をご利用いただいたお客様に、ご希望があれば環境に配慮した認証紙製を使用した容器をお渡しし、お料理を食べきれなかったときにご自身の責任でお持ち帰りいただく取り組みです。
これにより、食品ロス・ゴミの削減に取り組むとともに『食べ残したものは自分で持って帰る文化』の普及と啓発を図っていきたい」と松田顧問は話します。「この取り組みをホテル業界に広めたいと活動していますが、これまで、食べ残しの持ち帰りに伴う法的・衛生的な責任を高いハードルとして感じる事業者が多く、取り組みが進まない部分もありました。一方、食品ロスによる経済損失は大きく、温室効果ガス排出は気候変動に影響を及ぼすとの指摘もあります。今回、事業者・消費者(お客様)が安心して食べ残しの持ち帰りができるようガイドラインが政府により策定されましたので、ガイドラインを含め、mottECOの取り組みを広く普及していきたいと考えています。
「ブッフェに関しても、足りないことを恐れ大量に料理を出すのではなく、その量を見極めること、必要な量だけ発注していただくこと、余らない・食べきるというパーティーの意義を考え直すことも必要です」山本宿泊部長は語ります。「そこには、お客様の理解、旅行会社の理解、例えば修学旅行であれば、学校・学生・親御様の理解が必要ですし、理解していただくにはわかりやすさ・伝わりやすさも必要です。教育旅行でも環境に配慮した旅行って何だろう?とみんなで考えるプログラムを組むと勉強にもなり旅の印象にも残ります。全部を食べきることを一つの目標にして、それがクリアできたら認定書を出しみんなで喜びを分かち合う。まさにゲーム感覚で取り組むという発想の転換も必要ですね。」

松田顧問によると、ホテル業界全体では経営判断が必要とされない事項は取り組みが進んでいますが、mottECOの採用はまだ業界1割程度とのこと。リスクがあるとなかなか1歩が踏み出せないケースが多いように感じています。一方、CO₂排出量削減や気候変動をいかに軽減するか、日本は食料自給率が低いということも考えなければなりません。まさに今、課題とリスクをどう捉えるかが問われていますね。

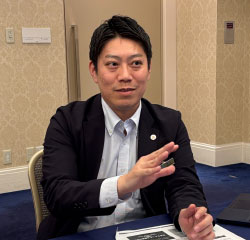
「CO₂ゼロSTAY®を導入したのは、実に自然な流れでした」と話す水上レベニューマネージャー。「元々社内では前述した環境配慮への取り組み文化が浸透していたため風土醸成ができていて、CO₂ゼロSTAY®の話をいただいた際、何の違和感もなくむしろ良い提案をいただいた、やりましょう!教育旅行にも取り入れたら面白いね、と即決でした。また、販売するにあたりストーリー性を持たせたいと思い企画を練っていたところ、バイオプラスチック素材による『土に帰るタンブラー』と縁があり、ホテルの40周年の冠をつけてCO₂ゼロSTAY®と組み合わせて販売しようという話になりました。このタンブラーは、プラスチック含有をできる限り減らすため植物由来成分94%となっており、植物由来であることからプラスチック臭がなく飲み物の風味を損ねることがない環境配慮と使い心地を兼ね備えた素晴らしいタンブラーなのです。」と水上レベニューマネージャーは自信を持った様子で話します。
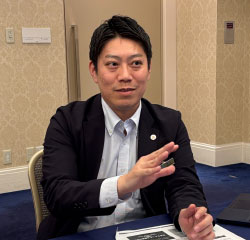
「2025年3月には『開業40周年記念宿泊プランCO₂ゼロSTAY®』としてプレスリリースも発信し、自分たちにとっても思い入れのある宿泊プランになりました。フロントにCO₂ゼロSTAY®証明書が置いてあると『今日も予約が入っているな!』と嬉しくなります。このプランは若い方から年配の方まで幅広いお客様にご利用いただいていますが、印象的だったのは予約された方は日本の方、宿泊される方は外国の方という予約がありました。お客様にお話を伺ったところ、外国のお客様を日本に招待するにあたりこのプランを紹介したかったとお言葉をいただき、大変嬉しかったです。」と山本宿泊部長から笑みがこぼれました。

ホテルメトロポリタンエドモントでは、照明器具のLFD化をはじめホテルの設備全般を見直し、CO₂削減またはCO₂を出さない取り組みを計画中です。また、「mottECO」の取り組みを全国の同業他社や飲食業界などへの普及活動も本格化したいと考えているそうです。
「CO₂ゼロSTAY®においては利用範囲を拡大し、2027年からは修学旅行の全宿泊に適用します。単に泊まるだけではなく、SDGsネイティブの学生のみなさんに事前学習でCO₂削減について学んでもらい、実際当ホテルに宿泊することでCO₂削減を体験してもらえるのは、本当にわくわくしますね!」と水上レベニューマネージャーは笑顔で語ってくれました。
「宿泊や食を扱う事業者であるホテルにとって、もちろん売り上げやお客様満足度、従業員満足度なども重要な事象ではありますが、世の中の社会的な役割を担うことも非常に重要で、事業者として一定の責務でもあります。それは環境配慮に対する取り組みやCO₂排出量削減の取り組みであり、それをセットでやることが今の時代では非常に重要な取り組みなのです。これからはそういった取り組みをしている事業者がお客様に選んでいただける対象になりますし、株主をはじめあらゆるステークホルダーからの理解や評価につながることになります。」と松田顧問は語ります。「一方、人の確保が難しい現状において、環境配慮の取り組みが後回しになってしまうケースもあると思いますが、環境に関する時間軸はかなり切羽詰まっています。海外でも気温が非常に高くなり日常生活が維持できないケースもあり、また日本でも気温上昇やゲリラ豪雨などをみなさんも体感されていると思います。今やらないとこの国で生活ができなくなってしまうかもしれない、私たちは事業ができないどころか生活ができなくなるかもしれない。そのため事業と環境配慮の取り組みは同時にセットでやることが重要です。誰かがやってくれるわけではなく、国、自治体、事業者、学校、消費者みんなで連携して取り組まないと持続可能な社会を維持できません。
例えば、リネンを毎日替えることはお客様サービスとして必要なのではないかと思い込んでいましたが、海外では環境配慮を考えやらないことが普通です。いざそれを実行してみたらお客様からのクレームもなく、結果、お客様の理解も進んでいることが分かりました。私たちが思い込んでいることをグローバルな視点でもう一度見直してみることも必要ですね。今できることから始めることが重要です。宿泊業界の脱炭素推進に向け、連携して一緒に取り組んでいきましょう」と松田顧問は熱意を持って語ります。
宿泊業界の脱炭素推進への期待がますます膨らみます。

左より、レベニューマネージャー 水上拓也様、顧問 松田秀明様、宿泊部長 山本哲也様(日本ホテル株式会社)
サービスに関する
ご質問・ご相談はこちらから